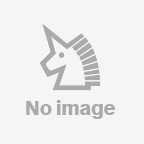5/31(水)は千里ライフサイエンスセミナー『エピゲノム情報に基づくがんの制御』に行ってきました。

参加者は製薬会社の方が多いのか(会社から来させられてる?)、
会場全体から製薬会社臭がしてましたwww
年齢層はバラバラで、女性は1割程度。
今回は演題が8つもあり、
各講義が30~40分(質疑応答含む)とめっちゃ細切れwww
量が多いので、演題によっては要旨のまとめみたいになるけど、許してね☆
(内容に誤りがあったり、著作権等に問題がある場合は、ご指摘ください)
*************************************************************************************************
【はじめに】by 油谷浩幸氏(東京大学先端科学技術研究センター 教授)
まずは「エピゲノムとは」というご説明。
がん細胞におけるエピゲノム異常の原因として、エピゲノム修飾因子自体の遺伝子変異や炎症などの周囲環境の変化が重要な役割を果たすことも示されつつある。
エピゲノム修飾を制御するタンパクには、
・writer
・eraser
・reader
・chromatin remodeler
がある。
本日のセミナーでは、エピゲノム制御を標的とした新たな治療戦略の可能性について模索する。
【演題①:細胞悪性化とエピゲノム異常】by 油谷浩幸氏(東京大学先端科学技術研究センター 教授)
油谷氏による続けての講義。次世代シーケンサーを用いたゲノム解析により、発がんにかかわるドライバー変異につながる主な遺伝子異常は、ほぼ同定されつつある。
【演題②:急性骨髄性白血病の制御に必須なヒストン制御因子】by 北林一生氏(国立がん研究センター研究所 分野長)
同氏らは、EZH1およびEZH2がAMLのがん幹細胞の維持に重要である(=逆に言えば、EZH1およびEZH2がなければがんは消滅する)ことを明らかにした。
EZH1とEZH2は、両方阻害しないとダメで、片方だけ阻害してもがんは再発してしまう。
今までH2の方に特異的な阻害剤は数社から出ていたが、その阻害剤ではH1の方は阻害されないため、
がんは再発してしまっていた。
同氏らは、第一三共と共同でEZH1/2二重阻害剤を開発し、その結果dormant LSCは死滅した。
また、変異型IDHは、野生型IDHと異なる活性を持つため、
変異型IDHに対する阻害剤が開発できれば、副作用はほとんどないと考えられる(=変異型IDHは自然には存在しないため)。
【演題③:iPS細胞技術によるがんエピゲノムの理解】by 山田泰広氏(京都大学iPS細胞研究所 教授)
エピゲノムはiPS細胞にも関係あるようです。
同氏らは、iPS細胞作製技術を、エピゲノム制御状態を積極的に改変するツールとして、がん細胞に応用することを検討しているそうです。
お医者さんって頭いいよね。
逆転の発想っていうか。
(昔勤めていた医療機器の会社でも、本来と違う医療機器の使い方を編み出した医師がいらっしゃって、
新しい適応での承認につながったことがありました)
がん細胞のリプログラミングによって、非がん性の細胞を作成できるかもしれないそうです。
EWS/ATF1をoffにするとがんが消滅し、EWS/ATF1を再びonにするとがんが再発しますが、
Wilms’ tumor modelでは再発に2~3ヶ月かかったのに対し、Sarcoma modelでは1~2週間で再発した。
再発までの期間が違う理由は、
Wilms’ tumor model ではepigenetic generationが原因であるのに対し、
Sarcoma modelではgenetic mutationが原因だからだそうです。
同氏は、「がんはゲノムだけではなく、場合によってはエピゲノムの病気でもある」と講義を結ばれました。
【演題④:エピゲノム修飾を介したオートファジー制御とがん】by 中西真氏(東京大学医科学研究所 教授)
オートファジーに特化した遺伝子改変マウスががん発症を促進することから、オートファジーの生理的機能の1つががん発症の抑制であることが明白となった。
同氏らは、オートファジーが活性化されることががんの防御に重要であると考えて、老化誘導がどのようにしてオートファジーを制御するのかを解析した。その結果、Fbxo22がオートファジー、リソソーム合成系の遺伝子発現に重要な役割を果たしていることがわかった。
細胞老化に伴い誘導されたFbxo22は、TFEBの転写を促進してオートファジーを正に制御することで、がん防御機能を果たしていることが予想された。
【演題⑤:ヒストン脱アセチル化酵素研究の新展開とエピゲノム創薬への展望】by 吉田稔氏(理化学研究所 主任研究員)
同氏らは、初の特異的ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤の発見を契機に、HDACの機能解析とヒストン修飾制御による疾患治療の可能性について検討を続けてきた。
1. 非ヒストンタンパク質のアセチル化・脱アセチル化
2. 長鎖脱アシル化
3. 代謝とリンクするHDAC酵素活性
のご説明。
【演題⑥:膵がん層別化治療を目指したエピゲノム標的探索】by 立石敬介氏(東京大学大学院医学系研究科 講師)
膵がんは難治癌の代表であり、有効な治療薬は十分ではない。
腫瘍を構成するがん細胞は個人ごとに異なり、かつ同一腫瘍内でも多様性が存在する。採取されたサンプルが生体内の状態を可能な限り再現したまま解析されることが重要である。
同氏らは当院(東大病院?)にて膵・胆道疾患の精査治療を行う患者の微量検体の一部を増幅培養し、その特性および腫瘍内多様性を維持したまま解析可能なPDX(Patient-derived Direct Xenograft) システムを構築してきた。
また、膵がんに対するエピゲノム関連分子阻害薬の効果を検討する目的で、100種類のエピゲノム関連分子阻害薬をin vitro PDO培養系を用いて増殖抑制効果のスクリーニング・解析を行っている。
【演題⑦:BRD4を標的とするケミカルバイオロジー】by 田中実氏(田辺三菱製薬株式会社 副主任研究員)
現在までに170剤以上の抗がん剤がFDA承認されているにもかかわらず、がんは未だにアンメットメディカルニーズが高い疾患である。
化学療法剤は重篤な副作用があり、臨床上のベネフィットは一般的に不十分であると言わざるをえないため、
新しいターゲットクラスに作用する抗がん剤が切望されている。
エピジェネティクス関連蛋白は抗がん剤の開発において非常に魅力的な標的分子である。
同氏が研究されているBRD4に対する低分子アンタゴニストは、世界では注目されているが、日本ではあまり知られていないそうです。
【演題⑧:胃癌で誘導されるエピゲノム異常と小分子を用いた領域特異的エピゲノム制御】by 金田篤志氏(千葉大学大学院医学研究院 教授)
細胞は様々な外的ストレスによりエピゲノム異常を蓄積し、それはがんにつながることもある。
配列特異性、投与への適用性、それぞれの特徴を持つアプローチに対し改良を進めることで、ゲノム領域選択的アプローチによるエピゲノム治療法の確立が望まれる。
*************************************************************************************************
次回の『生命を司り、操る~ノンコーディングRNAの底知れぬちから~』(7/7)にも、もう申し込んだよ♪(’ ー’ )
参加者は製薬会社の方が多いのか(会社から来させられてる?)、
会場全体から製薬会社臭がしてましたwww
年齢層はバラバラで、女性は1割程度。
今回は演題が8つもあり、
各講義が30~40分(質疑応答含む)とめっちゃ細切れwww
量が多いので、演題によっては要旨のまとめみたいになるけど、許してね☆
(内容に誤りがあったり、著作権等に問題がある場合は、ご指摘ください)
*************************************************************************************************
【はじめに】by 油谷浩幸氏(東京大学先端科学技術研究センター 教授)
まずは「エピゲノムとは」というご説明。
がん細胞におけるエピゲノム異常の原因として、エピゲノム修飾因子自体の遺伝子変異や炎症などの周囲環境の変化が重要な役割を果たすことも示されつつある。
エピゲノム修飾を制御するタンパクには、
・writer
・eraser
・reader
・chromatin remodeler
がある。
本日のセミナーでは、エピゲノム制御を標的とした新たな治療戦略の可能性について模索する。
【演題①:細胞悪性化とエピゲノム異常】by 油谷浩幸氏(東京大学先端科学技術研究センター 教授)
油谷氏による続けての講義。次世代シーケンサーを用いたゲノム解析により、発がんにかかわるドライバー変異につながる主な遺伝子異常は、ほぼ同定されつつある。
【演題②:急性骨髄性白血病の制御に必須なヒストン制御因子】by 北林一生氏(国立がん研究センター研究所 分野長)
同氏らは、EZH1およびEZH2がAMLのがん幹細胞の維持に重要である(=逆に言えば、EZH1およびEZH2がなければがんは消滅する)ことを明らかにした。
EZH1とEZH2は、両方阻害しないとダメで、片方だけ阻害してもがんは再発してしまう。
今までH2の方に特異的な阻害剤は数社から出ていたが、その阻害剤ではH1の方は阻害されないため、
がんは再発してしまっていた。
同氏らは、第一三共と共同でEZH1/2二重阻害剤を開発し、その結果dormant LSCは死滅した。
また、変異型IDHは、野生型IDHと異なる活性を持つため、
変異型IDHに対する阻害剤が開発できれば、副作用はほとんどないと考えられる(=変異型IDHは自然には存在しないため)。
【演題③:iPS細胞技術によるがんエピゲノムの理解】by 山田泰広氏(京都大学iPS細胞研究所 教授)
エピゲノムはiPS細胞にも関係あるようです。
同氏らは、iPS細胞作製技術を、エピゲノム制御状態を積極的に改変するツールとして、がん細胞に応用することを検討しているそうです。
お医者さんって頭いいよね。
逆転の発想っていうか。
(昔勤めていた医療機器の会社でも、本来と違う医療機器の使い方を編み出した医師がいらっしゃって、
新しい適応での承認につながったことがありました)
がん細胞のリプログラミングによって、非がん性の細胞を作成できるかもしれないそうです。
EWS/ATF1をoffにするとがんが消滅し、EWS/ATF1を再びonにするとがんが再発しますが、
Wilms’ tumor modelでは再発に2~3ヶ月かかったのに対し、Sarcoma modelでは1~2週間で再発した。
再発までの期間が違う理由は、
Wilms’ tumor model ではepigenetic generationが原因であるのに対し、
Sarcoma modelではgenetic mutationが原因だからだそうです。
同氏は、「がんはゲノムだけではなく、場合によってはエピゲノムの病気でもある」と講義を結ばれました。
【演題④:エピゲノム修飾を介したオートファジー制御とがん】by 中西真氏(東京大学医科学研究所 教授)
オートファジーに特化した遺伝子改変マウスががん発症を促進することから、オートファジーの生理的機能の1つががん発症の抑制であることが明白となった。
同氏らは、オートファジーが活性化されることががんの防御に重要であると考えて、老化誘導がどのようにしてオートファジーを制御するのかを解析した。その結果、Fbxo22がオートファジー、リソソーム合成系の遺伝子発現に重要な役割を果たしていることがわかった。
細胞老化に伴い誘導されたFbxo22は、TFEBの転写を促進してオートファジーを正に制御することで、がん防御機能を果たしていることが予想された。
【演題⑤:ヒストン脱アセチル化酵素研究の新展開とエピゲノム創薬への展望】by 吉田稔氏(理化学研究所 主任研究員)
同氏らは、初の特異的ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤の発見を契機に、HDACの機能解析とヒストン修飾制御による疾患治療の可能性について検討を続けてきた。
1. 非ヒストンタンパク質のアセチル化・脱アセチル化
2. 長鎖脱アシル化
3. 代謝とリンクするHDAC酵素活性
のご説明。
【演題⑥:膵がん層別化治療を目指したエピゲノム標的探索】by 立石敬介氏(東京大学大学院医学系研究科 講師)
膵がんは難治癌の代表であり、有効な治療薬は十分ではない。
腫瘍を構成するがん細胞は個人ごとに異なり、かつ同一腫瘍内でも多様性が存在する。採取されたサンプルが生体内の状態を可能な限り再現したまま解析されることが重要である。
同氏らは当院(東大病院?)にて膵・胆道疾患の精査治療を行う患者の微量検体の一部を増幅培養し、その特性および腫瘍内多様性を維持したまま解析可能なPDX(Patient-derived Direct Xenograft) システムを構築してきた。
また、膵がんに対するエピゲノム関連分子阻害薬の効果を検討する目的で、100種類のエピゲノム関連分子阻害薬をin vitro PDO培養系を用いて増殖抑制効果のスクリーニング・解析を行っている。
【演題⑦:BRD4を標的とするケミカルバイオロジー】by 田中実氏(田辺三菱製薬株式会社 副主任研究員)
現在までに170剤以上の抗がん剤がFDA承認されているにもかかわらず、がんは未だにアンメットメディカルニーズが高い疾患である。
化学療法剤は重篤な副作用があり、臨床上のベネフィットは一般的に不十分であると言わざるをえないため、
新しいターゲットクラスに作用する抗がん剤が切望されている。
エピジェネティクス関連蛋白は抗がん剤の開発において非常に魅力的な標的分子である。
同氏が研究されているBRD4に対する低分子アンタゴニストは、世界では注目されているが、日本ではあまり知られていないそうです。
【演題⑧:胃癌で誘導されるエピゲノム異常と小分子を用いた領域特異的エピゲノム制御】by 金田篤志氏(千葉大学大学院医学研究院 教授)
細胞は様々な外的ストレスによりエピゲノム異常を蓄積し、それはがんにつながることもある。
配列特異性、投与への適用性、それぞれの特徴を持つアプローチに対し改良を進めることで、ゲノム領域選択的アプローチによるエピゲノム治療法の確立が望まれる。
*************************************************************************************************
次回の『生命を司り、操る~ノンコーディングRNAの底知れぬちから~』(7/7)にも、もう申し込んだよ♪(’ ー’ )
- 関連記事
-
-
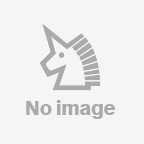 映画『メッセージ』観ました。
2017/06/17
映画『メッセージ』観ました。
2017/06/17
-
 優先順位が付けられない件。┐(’~`;)┌
2017/06/06
優先順位が付けられない件。┐(’~`;)┌
2017/06/06
-
 千里ライフサイエンスセミナー『エピゲノム情報に基づくがんの制御』の感想
2017/06/04
千里ライフサイエンスセミナー『エピゲノム情報に基づくがんの制御』の感想
2017/06/04
-
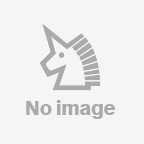 出張CiRAカフェiPS夜話『生きものすべては細胞から』の感想
2017/06/01
出張CiRAカフェiPS夜話『生きものすべては細胞から』の感想
2017/06/01
-
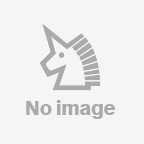 第1回JTF翻訳品質セミナー『誰も教えてくれない翻訳チェック ~翻訳者にとっての翻訳チェックを考える~』の感想
2017/05/23
第1回JTF翻訳品質セミナー『誰も教えてくれない翻訳チェック ~翻訳者にとっての翻訳チェックを考える~』の感想
2017/05/23
-